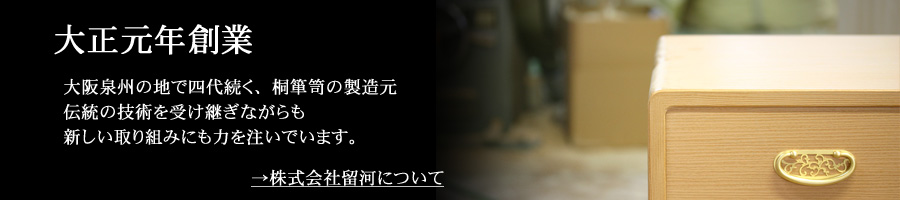桐たんす
湿潤な日本の独特な気候の中、着物を状態よく保管することが出来る≪桐箪笥≫
古くより引き継がれる伝統的な製法で気密性の高い桐たんすをお客様のご要望に合わせ作成しています。

大正元年創業。
歴史のある≪大阪泉州桐タンス≫の古き良き伝統の技を引き継ぎ、
≪大阪泉州桐タンス≫は、
良質な厚い桐材を使用し、組手が多く、
近年は、大切な着物、和服、高級衣類だけでなく
大切な衣類や、小物
バックを湿気から守る収納家具としてもご使用いただいております。
置きたい場所の大きさに合わせて。
入れたい服の量に合わせて。
お客様のご要望に合った桐たんすを職人が作成いたします。
手作りだからこそ細かなご要望にお応えできる事を活かし、
お客様のご利用環境に合った桐タンスを
オーダーメイドで製造しています。

思い出のあるお母様の桐たんすを
製品紹介
| 30万円~ | 天丸長持ち、天丸小袖タンス、等 |
|---|---|
| 70万円~100万円 | 天丸中衣装、胴丸小袖タンス、等 |
| 100万円~150万円 | 胴丸中衣装、胴丸昇タンス、等 |
| 150万円~220万円 | 胴丸ハシバミ戸、胴丸三枚戸、等 |
| 220万円~ | 総柾前無垢タンス、間(けん)ダンス |
| たんすの色 | お好みに合わせて色を選ぶことが出来ます |
|---|---|
| 盆の模様 | 模様を入れることができます |
このほか、お客様のご要望に合わせたサイズ、デザインで作ることができます。
30万円~

天地丸小袖
小袖タンスの天丸型
引き出しの段の数は4~10段まで作成できます。
着物や普段着を収納できる桐たんす
天丸長持ち
布団、座布団を入れるタンス。
胴丸型や座布団専用の座布団箪笥も作成できます。
70万円~100万円

胴丸小袖
小袖の胴丸型
引き出しの段の数は4~10段まで作成できます。
着物や普段着を収納できる桐の箪笥
天地丸中衣装
中衣装の天地丸型
最もオーソドックスなタイプのタンスです。
中央の開き戸にはお盆が入ります。
100万円~150万円

胴丸大開き戸
下に引き出し上には大開きを配置
戸内には壷型のお盆が七杯入り、透かし(ミシン)彫りを施してあります。
天丸型も選べます。
天地丸総盆
造幣局長賞受賞
京都の方に人気がある型で
たくさんの着物を収納するのに適したタンス
壷盆が15杯入っています。胴丸型もえらべます。
お盆に入れた着物は一目で見つけやすく、頻繁に着物をお召しになる方にお勧めです。
150万円~220万円

胴丸紫檀面ハシバミ戸
胴丸中衣装のワンランク上の型
上戸、中戸ともハシバミ戸(枠戸)になっており、紫檀をあしらったデザインになっております。
中央の開き戸にはお盆が入ります。
胴丸几帳面総盆ハシバミ戸
紫檀を使わず柔らかい印象を与えるようなデザイン
すべての開き戸をハシバミ戸(枠戸)にし、お盆は壷型で彫刻入り。10杯のお盆が入ります。
220万円~

胴丸紫檀面三枚戸
当社オリジナル
上戸の中央と、中戸の盆に彫刻が入っているのが特徴
盆は縁起の良い、鶴、松、竹、梅、亀の五杯
その他、ちょっとした仕掛けがあります。
胴丸几帳面三枚戸昇ダンス
胴丸紫檀面三枚戸)の型違い
紫檀を使わずスマートな印象を与えるタンス
開き戸、昇り、どちらでも選べます
箪笥の色
お好みに合わせて色を選ぶことが出来ます。
盆の飾り
華やかに、盆に模様を入れることが出来ます。模様無しもあります。

透かし彫り
縁起の良い、竹、梅などを彫っています

彫刻
縁起の良い、鶴、松、梅などを彫刻しています
特徴
- ・当社独自の色付け技術により、素手で直接触れても手垢がつかない(※別料金)
- ・他社と比べ、木の目(柾目)がまっすぐできめ細かく、仕上がりが美しい
- ・厚い材料を丁寧に組み上げているので、非常に丈夫である
- ・家の間取りやお客様の好みに合わせて、オーダーメイドによる製造が可能
- ・盆や引き戸に彫刻を施したデザインもあります。
- ・塗装の色合いを調合により、お客様のお好みで選べます
- ・当社オリジナルのデザインもご用意しております
- ・仕入れた原木の加工から製品に至るまで、すべての工程を当社で一貫しておこなっております
- ・それぞれの職人が組み立てから色付け、仕上げに至るまで、すべての工程を高い水準でこなせる技術力がある
-
板にする
黒く変色するまで雨が降ったりや日光が照り付ける中長期間干し、灰汁(アク)を抜き歪みをしっかり出し十分に乾燥させた桐材を使用し、作成する桐タンスに必要な板を作ります。
長期間使用する間に割れたり変形するのを防ぐために、切り分けた材を貼り合わせて板にします。
手間のかかる作業ですが、これをするとしないとでは桐たんすの見た目、使いやすさに差が出てきます。 
-
組手を抜く
大きく重量のある桐たんすを丈夫に組み上げるために組手を抜きます。
組手を抜いた板を金鎚で叩き込み組んでいきます。
組手には種類があり、場所に応じて合う組手を使い組み上げます。
大阪泉州桐たんすの特徴『組手が多い』にあるようにたくさんの組手を使用します。 
-
裏板を付ける
組んだ本体や引き出しに底板を打ちます。
固定する部分に木釘を打ち板をしっかり固定します。
打ち終わった木釘は、最終鉋(かんな)をかけ表面をきれいに仕上げます。 
-
鉋(かんな)をかける
組みあがった桐タンスの全体に鉋がけをします。
本体が二つや三つに分かれている桐タンスの表面を均一にし整えます。

-
抽斗(ひきだし)を仕込む
それぞれの引き出しの枠に合わせて前板をきっちりのサイズに調節します。
桐たんすは衣類を守るために気密性が高い作りになっています。
フタの役割をする引き出しの前板は、ピッタリ隙間なく収まるようにひとつづつ丁寧に具合を見ながら仕込みます。 
-
浮造り(うづくり)をかける
色を付ける前に、木目を美しく際立たせるための一手間。
全面に『浮造り』と呼ばれる道具を用い桐の木の木目を浮き立たせます。
この工程をすることにより仕上がりの美しさに差が出ます。 
-
色を付ける
お客様のお好みに合う色を付けます。
桐たんすの伝統的な色付けや、黒っぽい焼桐仕上げはもちろん
お好みや生活スタイルに合う色付けが出来ます。 
-
金具を付ける
抽斗(ひきだし)の取っ手、引き戸の金具
開き戸の蝶番、扉飾りの金具、鍵。
二つや三つ分かれの桐箪笥は棒通しと呼ばれる金具など。
飾り金具を付ける場合は、よりたくさんの金具を使用します。 
重厚感のある大阪泉州桐たんすの家具は丈夫で高級感もあり、

桐の材料の産地はアメリカ北部の材です。
国内では会津の桐が材料で有名ですが、
当社では昭和の中ごろから
加工方法は製材したものを
(乾燥が不十分だと割れてきたりします。)
 株式会社留河
株式会社留河